※この記事は2020年3月1日に公開した記事をもとに、内容を加筆修正し2023年8月22日に再公開したものです。
外構工事業は複雑な業種
外構工事と一口に言っても、みなさんもお家を建てるまでは知らなかったことばかりではないでしょうか。
このブログを読んでくださっているみなさんは、今まさに情報収集されているところだと思います。早速ですが、今日は外構工事の歴史や外構職人について詳しくご紹介します!
知っておくとためになる豆知識的な内容も含めて書いていきますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。

では早速やっていきましょう!
外構工事・エクステリア工事ってどういうもの?
「外構工事」の呼び名は歴史が浅い
外構工事、エクステリア工事はもともと工務店の仕事でした。
「外構工事」という明確な呼び名はそもそも存在しておらず、建物は大工工事、水道は設備工事、外周りは土木工事及び造園工事、という風に業種毎にきっちりと区分けされて呼称されていたのです。
例えば境界ブロックを積むにしても一筋縄ではいきません。「ブロックを積む」に至るまでにも多様な業者さんが入り、以下のような工程手順を踏むことで境界ブロックが完成します。

ブロック組積手順
- ブロックの基礎を作る為の掘削・床付け。担当は「土木屋さん」
- ブロックの基礎となるベースコンクリートを打設します。担当は同じく「土木屋さん」
- ブロック基礎の中に入る背筋(鉄筋)を設置します。担当は「鉄筋屋さん」
- ブロック本体を実際に積みます。担当は「ブロック屋さん」
このブロック組積手順はあくまでほんの一例ですが、いかがでしょうか?この工程だけ見ても境界ブロックを積むために3つの業種が登場しています。
このように一つの工事を行うごとに複雑化していた今までの構造を一つにまとめたのが、現在増えてきている「外構工事・エクステリア専門店」です。これについては後述しますが、外構工事・外構職人という複数の業種をひとまとめにした言葉が意識され始めたのは、この「外構工事・エクステリア専門店」が始まりです。
外構工事の範囲はそもそもどこまでなのか
いざどこかの業者に外構工事を依頼しようと思っても、いったいどこまでお願いしていいのかわからない。そういったお声をよく耳にします。
- 立水栓が欲しいんだけど、水道工事もできるのかな。
- ガレージのシャッターはどこに頼めばいいんだろう。
- 物置はホームセンターで工事もやってくれるんだろうか。
- タイルの張り替えも外構の職人さんに頼んで大丈夫?
上記以外にも、もっともっと色々ありますよね。
外構工事専門店はあらゆることに対応するとはいえ、このような業務を全て自分たちでこなしているわけではありません。
外構の土木工事を行うことを専門として、フェンスやカーポートといったエクステリア金物商品が取り付けできない業者さんや、その逆でエクステリア金物商品の取り付けしかできない業者さんなど。本当に業者さんによってバラバラに分かれます。
外構工事に含まれる内容
それでは、いわゆる外構工事と言われる項目ををザッと書き出してみますね。
- ブロック積み
- レンガ積み
- 石積み
- 石貼り
- タイル貼り
- 外壁塗装
- 水道工事
- ガス工事
- 舗装工事
- 排水工事
- 造園工事(植栽、生け垣他)
- 電気工事(照明、インターホン、エアコンの室外機他)
- 金物工事(カーポート、バルコニー屋根他)
- シャッター工事
等々、細かく書き出せばキリがありません。もっともっと出てきます。
外構工事ってこれかな?これも外構工事かな?そんな風にみなさんが思うような、すべての家廻りの工事がまさに外構工事なんです。
どんなことでも一度、担当してくれている業者さんに相談してみてください。

外構工事・エクステリア専門店はいつできた?
外構工事・エクステリア専門店という業態が始まったのは、今からおよそ25年ほど前になります。
少し曖昧な言い方をしているのは、実際に専門職業として認知されだした時期が不特定であるのが一つの要因です。
外構工事を支えてきた3つの業種
それまでの外構工事は大きく分けて3つの業種に分類されていました。
それが
- 土木
- 造園
- 左官、ブロック
です。
今もゼネコンや役所の工事など、大規模事業には欠かせない業種です。
現在も同じような業態を事業としている業者もたくさんありますが、当時は大手ゼネコンや役所の工事をメインとしており、一般個人宅の外構工事といった小規模工事は、メインの仕事が無い時期や、工事と工事の間にある少しの合間に手掛けていました。
今とは違う外構のイメージ像
この頃の外構といえば、造園家がプロデュースする大豪邸。
テレビや映画で見るような豪奢な日本庭園などが近いですかね。植木や石組みをふんだんに使ったお庭です。
今では外構に大きさは関係ありませんよね。工事自体の内容も、植物や石ではなくコンクリートや人工芝がメインです。
外構業界の資材は日々進化を続けているので、また近いうちに外構の常識が変わる日が来るかもしれません。なんだかワクワクしますね。
外構職人ってどんな人??
外構職人のできること
結論から言うと、なんでもできる人が多いです。
前項でもお話ししましたが、たくさんの職種が融合したものが外構工事であり、工事の作業工程の中で一通り全て経験している職人さんが多いのです。その中でもベテランの外構職人になると、本当に一人でどんな工事もしてしまいます。
外構社長が歩んできたヒストリー
職人さんといえども、最初は誰でも未経験からスタートします。
未経験の職人さんが、いったいどうやって複合職である外構職人になっていくのか。そこにはストーリーがあるんです。
私は最初、造園職人として職人のキャリアをスタートさせました。庭に植木を植えたり、樹形を整えるために刈り込んだり…みなさんが想像するであろう典型的な造園業です。
様々な植物を触る毎日を送っていたある日、造園工事中のお客さまから相談を受けました。
「立水栓を交換してほしい」
造園職人の私は、当然それまでに立水栓の工事など携わったことはありませんでしたが、困っているお客さまの声を聞いてしまうと、断ることができませんでした。
お客様の期待に応えて、なんとかしてあげたいと思ったからです。
私は分からないながらに必死に立水栓を交換する方法を調べて、無事交換工事を成功させました。その際にいくつかのコツも掴んで、立水栓の工事自体もマスターすることができました。
こうなってくるともうただの造園職人ではありません。これが外構職人への道の始まりでした。
その後もお客さまに何かを相談される度に
「なんとかしてみましょうか?」
とすすんで期待に応えてきました。
あくまで「何とか役に立ちたい」という気持ちからの挑戦でしたが、お客さまも私を信頼して任せてくださり、様々な経験を通して立派な外構職人となることができました。感謝ですね。
外構職人も目で仕事を覚える
職人さんにとって、家の外周りは関連業種・業者も多く、同じ現場で働いている他の職人さんのことを多かれ少なかれ見ています。もちろん職人さん同士で話もします。
そういったところから情報を得て、新たな業務を始めてみたり、挑戦したりしています。
若かりし頃(おそらく今もですが)たくさん失敗をして、たくさんお客さまに怒られて、たくさん学んできた経験が職人さんたちを形作っているんですね。
こうして、みなさんのご理解とご協力のもと、毎日あちこちで職人さんが育てられた結果、一通りなんでもできる外構職人さんが生まれています。
もちろん、本当になんでもできるわけではありません。専門性の高い工種(タイル工や塗装工など)は、協力業者に依頼する方法が一般的です。ただし、なんでも協力業者さんを頼る職人さんには注意したほうがいいかも知れません。
さらにもう一つ。職人さんの仕事は、技術の差ももちろんですが、職人さんの性格、気質で仕上がりが大きく変わります。
今も昔も、お互いが少しでも気持ちよく過ごせる環境が大切ですよね。外構工事の際は、ぜひ職人さんとのコミュニケーションも楽しんでみてください。

職人の趣味は仕事
私自身もそうなのですが、仕事が大好きです。
厳密に言うと、この職業(外構工事業)や共に働く仲間たちが好きなんです。
この「外構工事」という仕事に就いている人は、自分の仕事が大好きな人が多いです。誇りを持っています。
私が今までに出会ってきた職人さんたちも業界企業の社員さんたちも、お客様の笑顔を欲しています。小さな他者貢献を求めているんです。とても気持ちの良い環境ですよね。
職人さんを筆頭として、プランナーさんやデザイナーさんたちも、この仕事が趣味を兼ねているようなところがあって気合の入り方が違います。お客様と一緒により良いものを考え、ご提案する楽しみに魅了されているようです。
モノ作りをする職業ということで高い極みがあり、覚えることもたくさんあることが、極める楽しみを見出しやすい傾向があるのかもしれませんね。
最近ではDIYも流行っていて、一般の方も趣味として庭いじりやガーデニングを楽しんでいる方が多いので、趣味性の高い分野でもあることがお分かりいただけると思います。
業者を選ぶ際は、プランナーさんや職人さんとのフィーリングも大切にしていきましょう。

今現在、外構工事専門店は日本中に広く存在していますが、きっちりと丁寧な仕事ができている業者はまだまだ少ないのが現状です。
今後もこのブログを通して、みなさんに正しい外構工事業者の選び方や正しい情報をお伝えしていきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今後もためになる記事を書いていきます。
励みにもなりますので、よかったらコメントもお願いします。
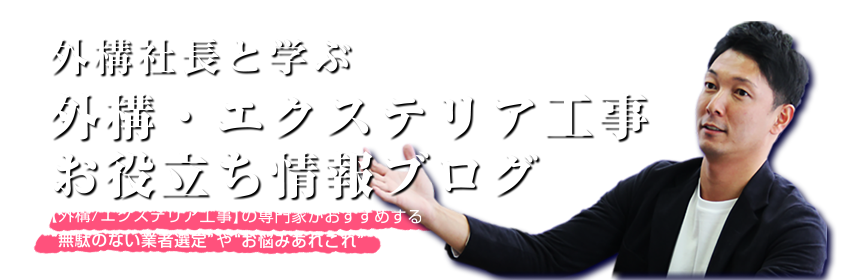
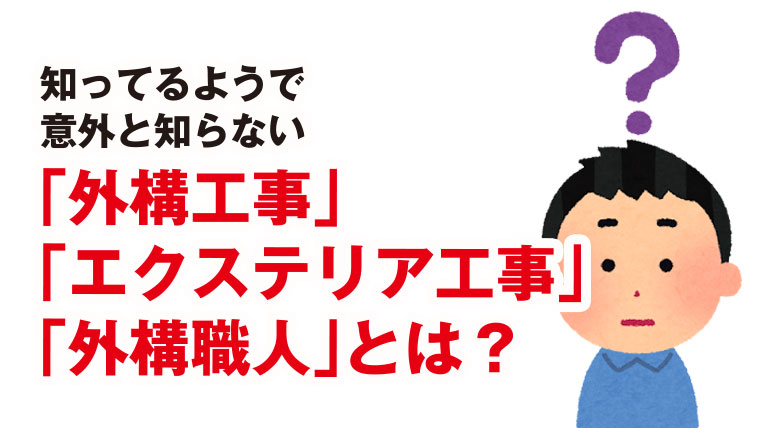

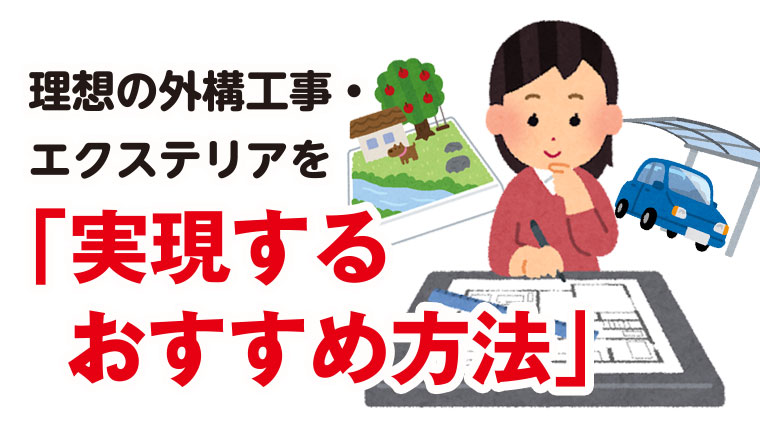

コメント